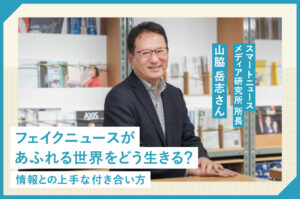新聞が「オールドメディア」と言われて久しい。新聞読者は減り続けているが、1997年生まれの漫画家・魚豊(うおと)さんは「本当は心のどこかで信頼している〝実家みたいな存在〟」だと語ります。人々の価値基準として説得力や納得感が重視される中で、新聞が「ファクト」を報じ続けることの意義を聞きました。
「新聞は実家みたいな存在」オールドメディアだけど、心のどこかで信頼している
―新聞にどんな印象を持っていますか。
新聞記者は、漫画家以外でやりたい仕事の一つでした。自分の足で真実を取りに行くのは、めちゃくちゃ魅力的な職業だと学生ながらに思っていました。新聞記者が登場する映画も好きです。特に好きなのは、神父による児童への性的虐待事件をすっぱ抜く米国の地方紙を取り上げた「スポットライト 世紀のスクープ」。実際に記者になったら、嫌なこともたくさんあるだろうとは思いますけどね。
―新聞の役割をどう考えていますか。
信頼できるメディアとして重要です。オールドメディアなんて言われていますけど、みんな本当は心のどこかで信頼している。新聞は実家のような存在だと思います。多様なメディアが登場し、流通している情報は玉石混交になっています。伝統的な方法でエビデンスを取る新聞の存在感はかえって増しているのではないでしょうか。
―普段、新聞を読んでいますか。
中学生の頃までは実家にあった子ども新聞や経済紙を手に取っていました。今は紙の新聞ではなく電子版を購読しています。普段はLINE(ライン)ニュースを見ることが一番多いかな。購読している電子版のほかにもインターネット上には新聞社の面白い記事がたくさんあるので、よく読みます。信頼性も高いです。ニュースから集めた情報を膨らませて、漫画のネタにすることもあります。陰謀論を扱った「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」を描いた時は、陰謀論集団「Qアノン」に関する記事を読み込みました。

漫画「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」の登場人物・渡辺拓也 ©️魚豊/小学館
ファクトを提示し続ける人がいるから社会が強固になる
―新聞読者は減り続けています。そもそもニュースは世間から求められているのでしょうか。
本質的な問題です。完全な個人主義が養成されつつあり、ある意味、社会が成熟しきった気はします。共同体の軽視というか、友達同士とか近場の人間関係の方が大事というか。それは理解できる部分もある。
―7月の参院選では報道各社が真偽検証に力を入れました。
参政党の躍進と合わせて注目していました。一部の有権者はもはや事実か否かではなく、説得力や納得感を重視しています。「FACT」を描いた時に思いましたが、事実を事実として信じてもらうのはとても難しい。おまえの話は信じないよと相手に言われたら、立つ瀬ないですから。それでもファクトを提示し続けることは絶対重要です。社会の底が抜けないのは、ファクトを提示し続けて、闘っている人がいるからだと思います。
―事実を事実として認めない人たちとの分断を乗り越えるために、新聞は何ができるでしょうか。
ファクトチェックとは別の角度で、説得する方法を考える必要があります。自然科学の正当性や根拠を担保しているのは、最終的には専門家に対する信頼です。それによって近代社会は発展してきたと思います。事実を事実として認めない人たちが現れるような信頼が崩壊した社会で、他者に考えを改めさせるには、心から対話を重ねるしかありません。他の国に比べて、日本には特定の政党の妄信的な支持者が多いわけではなく、対話の可能性は十分に残っています。

漫画「チ。―地球の運動について―」の登場人物・ラファウ ©️魚豊/小学館
魚豊さん(漫画家)
1997年生まれ。東京都出身。迫害を受けつつ地動説を追求する人々を描いた「チ。―地球の運動について―」(小学館)で2022年、手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。次作「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」(小学館)では陰謀論を扱った。陸上の100メートル走を題材にした「ひゃくえむ。」(講談社)の劇場アニメ版が25年9月に公開された。